

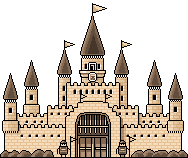
気分転換に旅先(モチロン仕事)での画像をお届けします!
(印象に残った画像を都度掲載予定です)
<近江八景> ※大津ガイドへリンク 比良の暮雪、堅田の落雁、唐崎の夜雨、三井の晩鐘、 粟津の晴嵐、瀬田の夕照、石山の秋月、矢橋の帰帆、 室町時代末期に選定されました。  「近江八景」は、鎌倉末・南北朝時代に中国よりもたらされた 「瀟湘(しょうしょう)八景」に由来する名所です。 中国湖南省を流れる瀟水と湘江が合流する辺りと 洞庭湖の情景を描いた瀟湘八景を手本とし、 京都や近江に来住した僧侶たちなどによって見出されました。 琵琶湖の広々とした眺めや四季折々の姿は印象的で、18世紀の 半ば以降になると、観光名所として大衆の間に広がりました。 また、歌川広重に代表される浮世絵版画に盛んに描かれるよう になり、日本を代表する名所として全国に広がっていきました。 |
||
 比良の暮雪 |
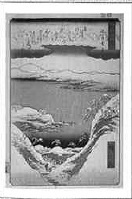 |
琵琶湖の西岸に沿って連なる 比良山系。 近江八景版画には、 その山々の雪に覆われた姿が 遠方から描かれています。 |
 堅田の落雁 |
 |
琵琶湖に浮かぶ 満月寺浮御堂の辺りに、 雁が列をなして 優雅に舞い降りる情景が、 名所となっています。 |
 唐崎の夜雨 |
 |
平安時代より、 水辺での身の汚れをはらう、 みそぎの地として知られた唐崎は、 朝廷の七瀬祓所の 一つといわれています。 雨にけむる荘厳な姿が印象的な 「唐崎夜雨」、 その初代の巨松は、 天正九年(1581)に 植樹されたと伝えられます。 |
 三井の晩鐘 |
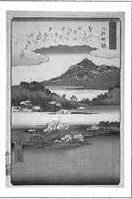 |
「三井晩鐘」の梵鐘は 600貫(2250キログラム) もある大きなもので、 音色のよいことで知られており、 形の平等院、銘の神護寺ともに 「音の三井寺」として 日本三銘鐘の一つ にも数えられています。 |
 矢橋の帰帆 |
 |
江戸時代、琵琶湖の対岸の 石場との間の渡し舟発着地 として栄えた矢橋は、 東海道を行く旅人が 大津から東へ向かう近道と してにぎわいました。 「矢橋帰帆」には、 その湖上を進む 帆船の群れが描かれています。 |
 粟津の晴嵐 |
 |
旧東海道の膳所から瀬田までの 松並木を描いた「粟津晴嵐」。 この“晴嵐”とは、 強風に枝葉がざわめく様子 を表しています。 旧東海道に沿った 湖岸の眺めはすばらしく、 晴天の日には伊吹山までも 眺められたほどです。 |
 瀬田の夕照 |
 |
幾多の戦乱の舞台となった 唐橋を描いた「瀬田夕照」。 別名「長橋」と呼ばれた 瀬田橋は、京都の交通、 軍事の要衝として重視され、 また時代の為政者の手によって 何度も架け替えられました。 |
 石山の秋月 |
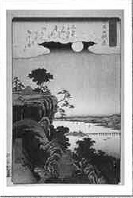 |
八月十五夜の美しい 月と石山寺を描いた「石山秋月」。 古くより、観音信仰の寺 として信仰を集めた 石山寺は、 奈良時代に創建されました。 |